白内障セッション
田淵 仁志(たぶち ひとし)
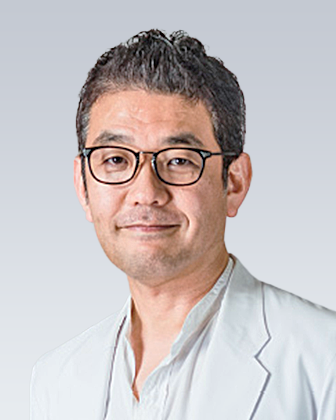
略歴
| 1997年 | 大阪市立大学医学部 卒業 |
| 2002年 | 大阪市立大学大学院医学研究科 修了 |
| 2003年 | 大阪市立大学医学部視覚病態学 助手 |
| 2004年 | 三栄会ツカザキ病院 眼科医長 |
| 2007年 | 三栄会ツカザキ病院 眼科主任部長 (現在に至る) |
| 2015年 | 名古屋商科大学経営学大学院 修了 |
| 2019年 | 広島大学大学院医系科学研究科医療のためのテクノロジーとデザインシンキング 寄付講座教授 |
| 2025年 | 兵庫医科大学AI眼科診療システム開発講座 特別招聘教授 |
専門医等
日本眼科学会認定・眼科指導医
日本眼科学会認定・眼科専門医
博士(医学・大阪市立大学)
修士(経営学・名古屋商科大学)
Executive MBA
日本眼科AI学会理事
日本白内障屈折矯正学会理事
日本白内障屈折矯正学会AI活用プロジェクト委員会委員長
白内障手術トレーニングの実情とAI指導の可能性
社会医療法人三栄会 ツカザキ病院 / 兵庫医科大学 田淵 仁志 先生
本講演では、白内障手術教育の安全域を“見える化”する二本柱――Section1:学習過程の定量分析とSection2:術中AIのリアルタイム解析の二つの視点を提示する。まずSection1として、ツカザキ病院眼科で初めて白内障手術を開始した初心者15名の0例目からの蓄積症例の総4,255例を用い、独自に設定した平滑化アルゴリズムと時系列データの変異点を数学的に抽出するPELT(Pruned
Exact Linear
Time)法を用いて15名のデータから得た蓄積症例数ごとの術中合併症率の変化点を検出し、学習が離散的な四段階で進むことを抽出した。術中合併症率は4段階で下記となった。〔第1期1–87例3.18%、第2期88–189例1.68%、第3期190–534例0.79%、第4期≥535例0.18%〕。平均0.53%という科内眼科医全体平均水準に到達する目安は535例で、経験速度は約123例で安定化した。初期50例の合併症率は3.1%、535例未満の術者が教育症例全合併症の40.9%を占め、535例までに要する期間は平均経験速度から約3.9年と推定された。さらに第1期から第4期にかけて手術時間は約48%短縮、切開幅はわずかに縮小し、最終視力は同等ながら早期視力回復は後期ほど速かった。これらは指導の集中度・症例配分・難易度設定・レビュー頻度を“段階適合型”に設計する実用的指針を与える(当院では最初の100例(前述の第1期)を助手顕微鏡で指導医と共に、101–200例(前述の第2期)はリアルタイム顕微鏡術野モニターにて指導医が遠隔監督という運用を実施している)。
次にSection2として、我々が研究開発途上のリアルタイム白内障手術技術評価AIを概説する。重要2工程(CCC、核処理)の識別はCCCと核処理を5秒の誤差範囲でリアルタイム同定し、開始・終了時刻の平均誤差は約5秒、重要2工程分類の平均正答率は96.5%であった。次に我々はこの重要工程分析AIをベースにした後嚢破損発生予測AIモデルを作成し、AUC
0.97の精度で後嚢破損を事前予測し、評価用後嚢破損症例動画データ44件中42件で執刀医や指導医より早く破嚢予知が可能であった。破嚢予知AIモデルを手術室で実装デモを行い、研修医に比べ上級医の統合リスク指標が有意に低く、処置時間も短かった。これらに加えて、我々は手術手技そのもののリアルタイム計測にも取り組んできた。その成果としてCCC時の角膜・切開・鉗子先端を高精度にリアルタイムで追跡可能となった。
今回の機会で、眼科臨床教育の1丁目1番地である白内障手術教育への統計学的アプローチと新しい技術(AI)を用いた取り組みを紹介しご理解いただければ幸いである。四段階モデルで教育の「いつ・どこ」を定義し、AIで「いま・ここ」の危険の立ち上がりを示す――両者の統合により、指導・症例選択・遠隔指導・術中AIアラート、AIによる技術評価までを実現するあたらしい白内障手術教育を示す。

